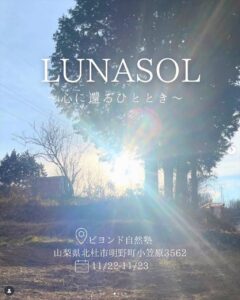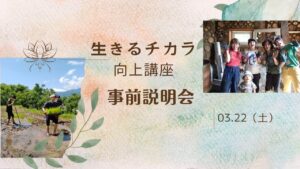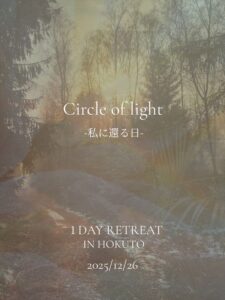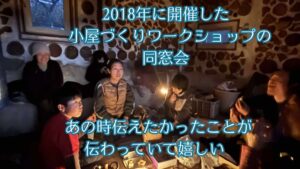先日の生きるチカラ向上講座で講座生に『失敗データを取る癖をつける方が良い』という内容を伝えたのですが、補足しないと難しかったかもしれません。
というのは、講座の翌日にスタッフの綾ちゃんと作業中、綾ちゃんがこんなことを言ったのです。
「菌ちゃん農法では土に埋めるものを30cmに切る必要があると書いてあったんだけど、ここらの竹はもっと長いから切るのが大変~」
自分はこの言を聞いて、「まさにそれだよ!その思考にハマっては、もったいない。」と思いました。
これ、どこがもったいないのかがわからなかったとしたら、前回話したことが伝わっていないことになります。
ということで以下補足:
物の破壊試験だとしたら破壊するまでやるのがあたりまえだが、成功させるのが目的の時の実験の仕方には注意が必要。
陥りやすい例:
農作業の時に日陰においてはいけないと種に書いてあると、多くの人は日向に植える。
私の提案:
あえて日陰にも植えてみる。日向だけに植えるのでもなく、日陰だけでもなく、両方やってみる。データとしてわかりやすいように日向から日陰まで段階的に植えて発育の違いを観察する。
この実験のメリット:
以下のことを知ることができ、後の作業効率を大幅に上げられる可能性がある。
・本に書いてある品種と違い、自分の植える植える種は日陰耐性があるかもしれない。
・どれくらいの日陰までならOKかのラインが見えやすくなる。
これらが体感としてあれば、次に植えるときの制約が劇的に小さくなる可能性がある。